※このサイトは綿半ソリューションズ株式会社をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
豪雨や台風といった気象災害のほか、地震や津波、火山活動による自然災害など、日本は多くの種類の災害リスクにさらされています。
災害が起きた場合、自走式駐車場は被害を軽減する事前の対策が求められるのと同時に、被災地域において大きな役割を担うことができます。
特に被害が広範囲に及ぶ地震では住民に安全な避難場所を提供できるほか、豪雨や津波の際には屋上部分が高台避難のスペースとなります。平時から車両や人が集まる場所にある駐車場だからこそ、災害発生時の一時避難場所の役割が浸透しやすいのです。
大規模商業施設や公共施設にとって、設置している自走式駐車場はBCPに重要な役割を果たします。
従業員や顧客の一時的な避難スペースとして安全を確保し、救急車両の活動拠点を提供するほか、救援物資や、事業継続に必要な物資の集積・配送拠点にもなります。
状況次第では事業・サービスを提供する代替拠点となるような駐車場を確保しておくことは、施設全体の防災力を高めることになります。
自走式駐車場の耐震性能は、構造方式によってさまざまです。
柱と梁を剛接合したラーメン式は、粘り強い変形で地震に耐えますが、揺れの幅が大きくなる傾向があります。柱と梁にブレース(筋交い)を入れたブレース式は、地震の揺れにブレースで耐えるため、揺れ幅は小さくなります。フロア全体が緩やかに傾斜している連続傾床式は、構造的に複雑になりやすいことから挙動の予測が難しいことがあります。
耐震性能を高めるため、制振装置や免振装置を導入するケースが多くなっています。地震による被害を小さくできるメリットはありますが、導入やメンテナンスのコストを考慮しておく必要があります。
自走式駐車場の耐震対策において、柱や梁、スラブの補強や、接合部を強い設計にすることは極めて重要です。
地震発生時の荷重伝達経路を明確にして局所的な破壊を防ぐため、柱や梁は炭素繊維シートを巻きつけ、スラブはコンクリートの打ち増しや鋼板を接着するなどして補強します。接合部は高力ボルト接合や溶接接合の強化、ガセットプレートの増設などが有効です。
自走式駐車場は、被災後もすぐに使用を再開できる程度に被害を抑えられる耐震性を確保する設計が必要です。
設計震度は建築基準法で定められたものより一段引き上げ、震度7相当の地震動に対しても、簡単な補修で使用可能になるレベルを目指します。
自走式駐車場の浸水・排水計画を策定する際には、まず国や自治体が公開しているハザードマップから、建設予定地の浸水リスクを確認。その上で、建物の設置高さや床レベルを検討します。駐車エリアだけでなく、電気設備や機械設備は最大浸水深よりも高い場所に設けるのが原則です。
1階部分を壁のない柱のみの構造(ピロティ)として浸水による影響を最小限にしたり、開口部をできるだけ小さくしたりする設計も、被害軽減対策として有効です。
自走式駐車場は、豪雨の際でも雨水が建物の中に流入しないようにする対策が必要です。
出入口などの開口部に止水板を設置すれば建物内への浸水を防ぐことができるほか、地下階の床や壁を防水シートで覆うことでも被害を防ぐことができます。
地下階やピットなど自然排水が難しい場所に排水ポンプを設置し、自動的に稼働させるシステムも有効。非常用電源を確保することで、停電時でも排水機能を維持できます。
自走式駐車場の水害・豪雨対策は、雨水を適切に管理することが重要で、透水性舗装や雨水貯留施設が大きな役割を果たします。
透水性の舗装やコンクリートは雨水を地中に浸透させるため、路面の水たまりを防止し、歩行者や車両の安全性を向上させます。
敷地内に雨水貯留施設を設置して一時的に貯めた雨水は、制御システムにより下水道や河川の排水能力に合わせて徐々に排水することで、都市型洪水の抑制につながります。
自走式駐車場の台風や強風に対する対策として、風荷重に耐えられるような構造設計や、飛散物防止は欠かせません。
主要な構造部材や接続部は想定される風荷重に十分耐えられる強度を確保し、十分な耐力のある基礎により建物の浮き上がりや転倒を防ぎます。
水平方向の剛性を高めるには、耐風ブレースや耐力壁などを追加するのも有効です。さらに、各階の外壁やルーバー、屋上設備は強風に耐えられるよう補強しなければなりません。
自走式駐車場の屋上階に設置されるさまざまな設備や広告看板は、台風や強風に備えてしっかりと固定しておく必要があります。
太陽光パネルや看板、照明器具などが強い風でも飛ばされないようにするため、屋上防水層を保護しつつ、構造躯体や基礎にボルトやアンカーで固定しておきます。
看板などは風荷重を考慮した形状や面積にすることも重要。各種の設備は、大型クレーンや高所作業車での施工手順を踏まえた設計にすると効率的な作業が可能になります。
自走式駐車場の窓ガラスが台風や強風で破損するのを防ぐには、飛散防止フィルムをガラスの内側か外側に貼るのが有効です。
必要に応じて、保護板やシャッターを設置するのも良いでしょう。合わせガラスや強化ガラスといった耐風性が高いガラスを採用しておくと、より安全性が向上します。
開口部は風洞実験や数値シミュレーションで風圧を検証し、どの程度の対策が必要かを見極めておきます。
自走式駐車場での車両火災への対策としては、早期発見と初期消火が重要なポイントとなります。
火災は自動火災報知装置や監視カメラにより、できるだけ早い段階で覚知できるようにし、スプリンクラーや消火器といった消火設備を適切に配置して、初期段階で確実に消火できるようにします。
排煙計画を定めておくことが安全性の向上につながるほか、防火シャッターや防火壁を設けて延焼を最小限に抑える対策も必要です。
自走式駐車場の利用者の安全を確保するには、避難経路や非常口を適切に配置する必要があります。
特に大規模な駐車場では、避難経路や非常口は複数を建物全体に分散して配置し、火災で使えない部分があっても安全に避難できるようルートを設計します。
避難すべき方向や非常口を分かりやすく示す標識を設置し、夜間や停電時でも視認可能な照明を確保します。
防火地域内の自走式駐車場の建物仕様は、建築基準法で厳しく制限されています。
防火地域では、3階建て以上、または延べ面積100㎡を超える建物は、火災に強い耐火建築物とする必要があるためです。
準防火地域でも、4階建て以上、または延べ面積1500㎡を超える場合も、同様に耐火建築物にしなければなりません。ただし、自走式駐車場のように開放性の高い建物で一定の要件を満たせば、耐火性能の基準が緩和される場合があります。
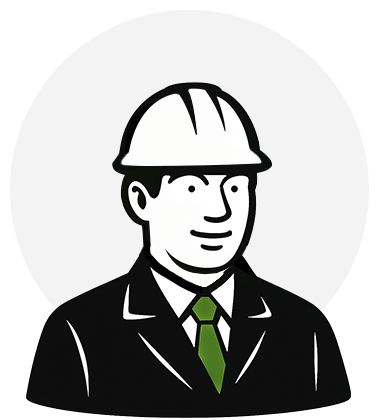

積雪地域においては、構造体の耐雪強度に関する認定を取得しており、雪荷重下でも車両が安全に利用できる構造設計を実現しています。豪雪地帯(2.5m〜3m超)への対応は個別検討が必要です。
沿岸部においては、塩害リスクを考慮し、照明や消火設備などを防錆仕様に変更。構造体自体は共通としつつ、海側では全面メッキ、内陸部では外側のみメッキ+内側塗装とするなど、コストと耐久性の両面で地域に応じた対応を行っています。
自走式駐車場のBCPにおいて、非常用電源やバックアップシステムは、事業の早期復旧や、安全確保に不可欠な設備です。
災害による停電時でも、排水ポンプや照明、エレベーターなどを稼働させるには非常用電源が欠かせません。発電機や蓄電池の導入が考えられるほか、配電盤を災害の影響を受けにくい場所に設置するよう設計することも検討に値します。
駐車場管理システムや顧客データのバックアップも事業継続には重要です。
被災後の自走式駐車場を迅速に復旧するには、設計段階から工夫すべきことが数多くあります。
耐震性や耐風性を向上させることはもちろんですが、もし建物に被害が生じた場合でも、補修が容易な構造や仕上げにしておけば、復旧までの時間を短縮できます。
部材のユニット化やプレキャスト工法の導入により、交換や修理を短期間で行える設計にするのも有効でしょう。
災害発生時、自走式駐車場は避難スペースや物資集積場所として大きな役割を果たします。
過去の災害時でも、大型商業施設や公共施設で駐車場を避難場所として活用した実例があります。
大規模な駐車場は車両を移動させれば大規模な空間を確保できることから、水や食料、医薬品といった救援物資の一時的な保管場所となるほか、避難者を受け入れたり、仮設事務所や作業員の休憩スペースなどを設置したりできます。
災害対策の内容や施設規模によって異なりますが、一般的に構造補強・防水・止水・非常用電源・スプリンクラー設備などを加えると、総工費の3~15%程度増加するケースがあります。
免震や制震構造を導入する場合はさらに上昇しますが、BCP(事業継続計画)や災害拠点としての機能を持たせるなら、長期的な価値として見合う投資と考えられます。
いいえ、止水板は入り口からの流入を防ぐための一時的・局所的な対策であり、根本的な対策としては排水ポンプの多重化、非常用電源の確保、床レベルの設定、敷地外排水設計の見直しなどが重要です。加えて、透水性舗装や雨水貯留槽の併用も都市型水害対策として有効です。
駐車場の規模や階数、開放率により、消防法および建築基準法の規定に適合する防災設備の設置が必要です。
また、開放型駐車場(外周開口率50%以上)であれば、自然換気で排煙が足りることもありますが、閉鎖型や地下階ではスプリンクラーや機械排煙設備が必要になります。
詳細は自治体の消防署・建築指導課との協議が必須です。
災害時に避難スペースや物資集積場所として活用する場合、以下の設備や機能が考えられます。


綿半ソリューションズ株式会社は、自走式立体駐車場の設計・施工を専門とする専業メーカーです。
全国に多数の施工実績を持ち、用途や敷地条件に応じた構造提案を行うほか、設計段階からゼネコンや設計事務所と連携し、図面・法規・運用面まで一貫して対応。
6層7段構造において国土交通大臣認定(一般認定)を2016年12月、業界で初めて取得※するなど、大規模・高層対応の先駆的な実績も有しています。



当メディアは、自走式立体駐車場の設計・施工に関わる専門知識を、実務目線で分かりやすく整理・発信する情報サイトです。構造・法規・寸法・防災・SDGs対応まで、多角的なテーマを扱いながら、建築・開発関係者の判断をサポートすることを目的としています。
制作・運営は、多数の業界特化型メディアを展開するZenken株式会社が行っています。
災害対策の取り組み
自走式駐車場は、外壁がない構造を活かし、津波を受け流す避難タワーの代替として提案されるケースが増えてます。階段に比べて車椅子でも避難しやすい点も強みです。
国交省・経産省と連携した補助金制度の適用も視野に入り、現在ではトイレや備蓄倉庫などを併設した認定例も存在します。地震や内水氾濫への対応を求める自治体向けに、平時と災害時を両立する施設計画が可能です。
自走式立体駐車場が3.11の震災時に耐えた映像がYouTubeにアップされています。その開放性によって建物の広い部分を津波が通り抜けているのがわかります。